病院で使われる言葉の中には、同じ言葉でも医療者が普段使っているニュアンスと患者側が受け取るニュアンスが異なりやすいものがあります。
今回は「良性」と「軽症」について具体例を挙げて解説していきます。
医者が「良性・軽症」と判断=まったく心配がない というわけではないのです。

「良性」:医者側が伝えたい意味と患者側の受け止め方の差
- 医者側の良性:治療するべき病気の状態。治療しましょう。
- 患者側の良性:良性だから大丈夫、正常でしょ、ほっといても心配ないでしょ。
患者側からは、良性というと、「良」の字もあり、何か良いもの=善である印象を受けます。
良性でした=異常なしととらえる人も多いのではないかと思います。
医者側が良性と伝えることが多いのは、何かしらの「できもの」があったときに、細胞や組織を一部とって、顕微鏡で見る検査(=病理検査)の結果で使用することが多いです。
この時、Ⅰ~Ⅴ段階に判定が分けられており、異常なし判定はⅠだけなのです。Ⅰ~Ⅴは以下のような意味です。
- Ⅰ:正常な細胞・組織
- Ⅱ:炎症に伴う変化が起きた細胞・組織
- Ⅲ:癌ではないが、ゆっくりと増殖する素質を持った細胞・組織=良性とも表現される
- Ⅳ:癌の可能性がある細胞・組織が疑われる(ⅢとⅤの間)
- Ⅴ:癌細胞と判断できる細胞・組織=悪性と表現される
Ⅰ、Ⅱは「できもの」ではないという判断です。
Ⅱは炎症が収まれば元の細胞・組織に戻る判定となります。
ただし、Ⅱの場合でも変化のある細胞・組織の判断であり、時間がたっても同じような状況だった場合、再検査するとⅤの判定になる(悪性腫瘍)こともあります。
Ⅲは良性腫瘍と言われやすいものです。
「できもの」ではあるので、時間経過でゆっくり自己増殖する素質はあります。
悪性腫瘍と違うのは、本体と違う場所に転移するほどの能力はないということです。
その腫瘍本体を切除したら、治癒完了になります。
そのため、良性と言われても治癒するには切除が必要となります→異常なしではないのです。
Ⅳ、Ⅴに関しては、基本的には悪性腫瘍(癌)として考えていきます。こちらは誤解しないと思います。
医者が良性といっても、異常なしではなく、放っておくと徐々に大きくなりますよ、切除したら治りますよという意味になります。
切除後の結果で良性でしたと言われたら、とりあえずの治癒まで終わったので大丈夫ですという受け止めでいいです。
しかし、また同じような腫瘍ができる可能性があるなら、定期検査を続けましょうというお話につながります。
医者側の「良性」とは、良の字であっても善ではなく、立派な病気。治療対象のものということになります。
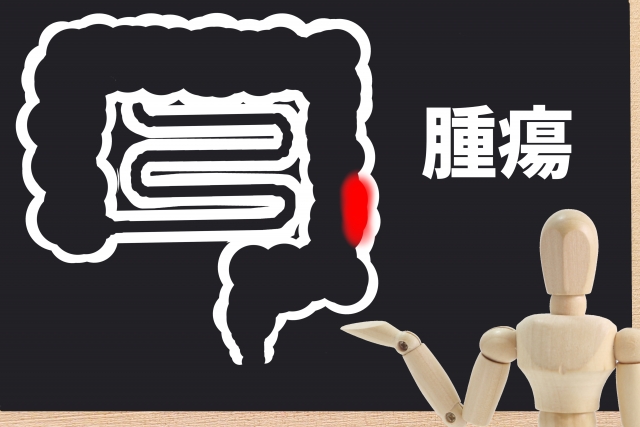
「軽症」:医者側が使う意味と患者側の受け止め
- 医者側の軽症:その病気の中では、一番病状が軽い状態。だけど病気自体が重病だから、ちゃんと治療しましょうね。
- 患者側の軽症:軽症?たいしたことないってことだよね。すぐ治るでしょ。もしくは、こんなつらいのに軽症?そんなわけないでしょ。どうなってんのよ?
医学的全体で軽症と規定されているものはなく、病名・病状ごとに重症・中等症・軽症と分かれています。
だから、軽症といっても実際は入院治療が必要なものから、本当に軽い病状まで含まれてしまいます。
例えば、新型コロナ感染症の軽症では、肺炎がないことのみが条件です(SpO2 ≧96)。
熱が高くて、咳がひどくても、肺炎がないと軽症と分類されます。
だから、状態によってかなりしんどい時でも含まれてしまいます。
災害の時にだれを先に治療するかというトリアージというものがあります。
トリアージでも軽症という区分があります(外来で処置可能、緊急搬送不要)。
条件は「自分で歩ける」だけです。
たとえ、腕が骨折してようがフラフラでも自分で歩ければ軽症というわけです。
急性膵炎という病気があります。
これも重症度が言われており、状態・症状、血液検査、画像検査などで判断しますが、
たとえ軽症でも死亡率が5%以下とはいえ、生命にかかわる病気になりますので、軽症でも入院治療を強く推奨されます。
「軽症」においても、病気の種類にもよって、症状が強くなくても決して軽く見てはいけないものから、
状態がどんなにつらくても軽症と定義されるものまで幅広く含まれます。
まとめ
「良性」・「軽症」といった言葉は、一見よさそうに見えても、実際は注意しないといけない可能性を含みます。
医者側からの言葉を都合の良いように考えて悪化させないように、何か引っかかるようなことがあれば、医師などに確認をしてみてください。



コメント