咳をしたことがない人はさすがにいないはずですが、咳で病院に行ったことがあるかというと、人それぞれと思います。
ただ、新型コロナ感染が広がってから約5年以上経ちますが、まだ感染することも多く、咳が続けば病院受診をする人も多いです。
ただ実際にどのくらい咳が続くと注意したほうがいいのでしょうか?
「内科でいいの?呼吸器内科のほうがいいの?」
「そもそも原因は何なの?」
「市販薬使ったけど良くならない、漢方薬のほうがいいの?」
「痰もでてきて、がんの可能性もあるの?」など 疑問が多くでると思います。
このページだけで全ての疑問が解消しますので、安心してください
今回は、
そもそも咳とはどういうものか、
人にうつる可能性がある咳はどのくらい続くのか、
原因を考える上で咳が続く期間が重要、
の3つのポイントを中心に解説していきます。
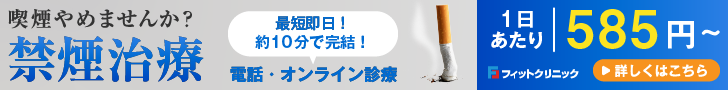
咳とはいったい何なのか?

咳の定義
肺や気管などの呼吸器に分泌物や異物(ほこりや痰なども含む)が入り込んだ時に、それらを空気とともに強制的に外へ排出しようとする生体防御反応・反射のこと
咽頭や気道の粘膜表面に咳受容体というセンサーがあり、ここが刺激されると咳反射で出現します。
異物を外に出す防御機構であり、無意識の反射行動のため、自分では止めにくい反応です。
痰を伴うか伴わないかで、湿性咳嗽(痰を含む)と乾性咳嗽(痰がない)の2種類に分けられています。
咳の原因
ほぼすべての呼吸器疾患が咳の原因となり、
ほかには循環器疾患(心不全、肺血栓塞栓、不整脈)や消化器疾患(胃食道逆流症)、耳鼻科疾患でも生じることがあり、
かなり広い領域の病気から症状として出てくる可能性があります。
喘息がない成人一般でも約10%が3週以上続く咳を自覚したことがある(日本内科学会雑誌109巻10号より)といわれ、
比較的長く続くこともまれではありません。
病院に行く決め手
咳は防御反射のため、完全になくすのは難しいです。
咳で日常生活がどのくらい邪魔されているかで判断することをお勧めします。
具体的には
- 寝付くときに咳で眠れない
- 咳が出て夜に起きてしまう
- 仕事中に咳が出て、頻繁に中断しないといけない
- 人とかかわる仕事でうつす病気だと困る(確定できるものは限られる) など
治療目標も上記の症状が改善できれば良しとしています。
咳が完全になくなるまでには原因によって長くかかる場合もあり、時間経過でも改善しない場合はより精密検査が必要になるので、その時も受診をお勧めします。
咳でかかる科は?
出現してすぐの咳に関しては、幅広い原因があり、かつ、ウイルス感染に伴うものが多いため、一般内科であれば、特に問題なく対応できると思います。
目安として1か月以上続くような咳の場合は、
画像検査ができる病院での内科受診か、呼吸器内科での診察が望ましいと思います。
人にうつす可能性のある咳はどのくらい続くのか
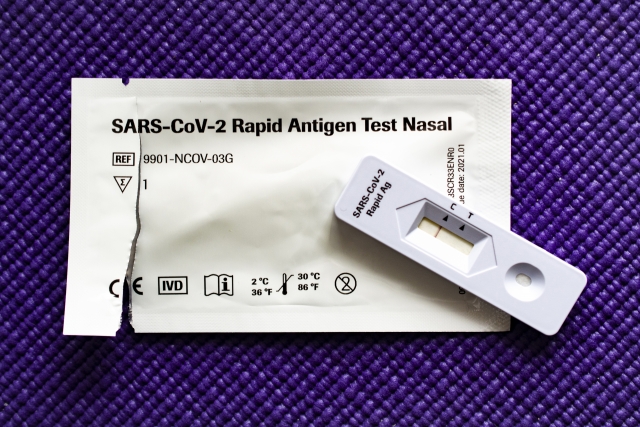
咳が続く期間で急性咳嗽、遷延性咳嗽、慢性咳嗽の3つに分けて考えられています。
人にうつす可能性があるのは基本的には遷延性咳嗽までと考えています。
遷延性咳嗽の場合、原因が多岐にわたってくるため、そこで病院受診をしてある程度の検査をしていけば、人にうつる可能性のある咳は除外できるはずです。
基本的には約10日前後で感染性はなくなるのが大半、
稀なものでも1か月程度の持続の時に病院での検査で感染のある・なしが判明できるはずです。
咳が出る原因究明:咳が持続している期間で分けて考える
急性咳嗽
3週間以内で終わる咳のことで、
病院受診をする咳の人の多くは発症後1週間以内で来院し、その原因の80%以上は感染症といわれています。
ウイルスや細菌などの病原微生物が気道に影響して起こるもので、この場合は人にうつす可能性があります。
急性上気道炎(風邪)の場合、発症後3-5日でピークを迎え、
10日目を過ぎても20%以上の人で継続しているという報告があります。
長くなる要因としては、はじめはウイルスなどによる反応で出ていたものが、
その後傷ついた部分を中心に過敏性が強くなる反応が起こります(感染後咳嗽といいます)。
この時は咳は出ても、その中にウイルスなどの異物はなくなった後のため、人にはうつらない咳になっています。
しかし症状からは区別ができないのが実情です。
急性咳嗽なら、経験的に10日目ぐらいまではうつる可能性がある咳として注意し、
それ以降はうつらない咳というのを一つの目安としています。
この気道過敏性が改善する時間が個人差の大きいところです。
基本的には時間とともに消失していき、1か月以上続くことは稀とされています。
細菌が原因の場合、やはり抗生物質の治療がないとより症状が長引き、人にうつす可能性のある期間も長引きます。
急性の咳が出る有名な細菌はマイコプラズマ、百日咳があります。
なかなか症状から判別するのは難しく、状況証拠(周りに同じような人がいたなど)や検査での確認も行い対応していきます。
この時に行われる検査は、主に感染症がどこまで悪さしているかになるので、感染症の迅速検査(インフルエンザやコロナなど)や
採血や胸部Xp、状況に応じて胸部CTで肺の画像を確認するぐらいにとどまります。
遷延性咳嗽
発症してから3週間~8週間まで続く咳をいいます。1-2か月続く咳というと、かなり長い印象をうけます。
この時期から原因として感染性よりも非感染性のものが多くなっていきます。
ただ、まだ感染性のパターンもあり注意が必要です。
感染性の場合:百日咳や肺結核、非定型抗酸菌症という結核の仲間(人にうつるものではない)などがあります。
非感染性の場合:肺以外の可能性がでてきます。
もちろん多いのは肺の病気(喘息、COPD(たばこ肺)、肺がん、慢性気管支炎、気管支拡張症など)ですが、
心臓由来や消化器由来、薬のアレルギーや耳鼻科由来の可能性も考えて、ひとつずつ確認していきます。
疾患が幅広くなるため、検査も先ほど挙げて採血、Xp、CTに加えて、
痰の検査や呼吸機能検査(肺活量などを調べる=COPDの診断)も行っていきます。
最初の診察だけで、確定をするのはかなり難しく、経過を見ながら、検査の計画などを進めていくことが多いです。
よってかなりの時間を要していきます。
感染性のものなら、いろいろな検査で確定しやすくなってきている時期のため、
人にうつる咳としての対応が必要かどうかはある程度判明できるはずです。
ここまで咳が長引く=すでに咳止めを使用しても改善しないということになります。
漫然と咳止めの内服のみを使っても結局改善せず、別の病院へ行く方も増えます。
診断確定に時間がかかることもあり、それまでの状況から追加される投薬を考えて行われます。
例えば、喘息やCOPDで使う吸入薬、抗アレルギー剤、食道炎対策の胃薬、副鼻腔気管支症候群の時に使うエリスロマイシン少量継続投与などを状況に合わせて選択し経過を見ていくことが多いです。
慢性咳嗽
8週間以上続く咳のことを指します。
2か月以上になるので、かなり長い期間続くことになっています。
原因としては感染性よりも非感染性が主体、痰を伴わない乾性咳嗽が多くなります。
ここまでくると咳で何か人にうつすものが隠れているということは、稀になります。
乾性咳嗽の慢性化:咳喘息、アトピー咳嗽(喉頭アレルギー)、胃食道逆流症が代表的。
- 咳喘息:咳が夜間から早朝に強く、日中は軽度 気管支拡張薬(吸入薬)が効果的。この場合2年程度は吸入ステロイドを継続することを推奨。
- アトピー咳嗽・喉頭アレルギー(慢性):咳が季節性に悪化、日中に多い。
- 胃食道逆流症:嘔吐しそうな咳が主体 胃酸分泌抑制薬が効果的。胸やけがない場合もある
湿性咳嗽の慢性化:副鼻腔気管支症候群(気管支拡張症など)、慢性気管支炎、COPD
- 副鼻腔炎気管支症候群:CTや痰の検査などで、ほかに病態がない場合はエリスロマイシン内服を使用。8週間程度で徐々に改善してくる。
- 慢性気管支炎、COPD:禁煙が必須。吸入薬など、肺機能なども併せて対応していく。
痰の有無は経過中に行った治療などにも影響されるので、一概に判断するのは難しいです。
あくまで、一般的な指針としてとらえてください。
慢性咳嗽の期間まで症状が続いていたのに病院に行かなかった場合は、まず遷延性咳嗽で挙げた検査を行ってからの結論になります。
咳を止める薬は?
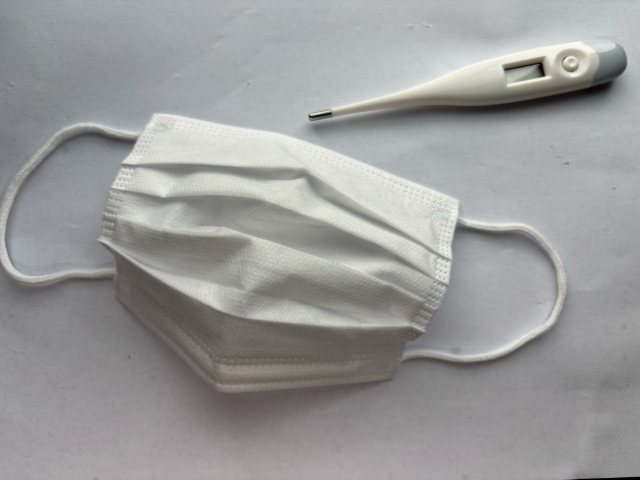
市販薬の中にも含まれる鎮咳薬を基本に使用していきます。
ただ、防御反射を完全に止めることは難しいため、あくまでなくすというよりも、咳で日常生活が妨げられないようにするというのが目標になります。
急性咳嗽であれば、鎮咳薬+必要なら抗生物質で、あとは時間とともに改善するはずです。
遷延咳嗽以降では、鎮咳薬とさらに原因に合わせた投薬になっていきます。
画像検査などではっきりした原因がなく、かぜ症状の後に遷延する咳嗽の場合は、喘息と同じようなメカニズムで気道過敏性が亢進していると考え、吸入薬を併用することも考慮します。
ただ、原因によっては逆効果になることもあるので、治療しつつも診断を進めていくことが重要です。
咳で使う漢方薬の代表は「麦門冬湯」と「小青竜湯」の2種類でしょう。
ちょっとした使い分けとしては、
麦門冬湯は少し潤いを与える作用があるので、乾いた咳に使いやすいです。
小青竜湯は水分を出す作用があるので、痰がらみなどが多くて咳が出る場合には効果が発揮されやすくなります。
まとめ
- 咳とは防御反射であり、自分で止めることも完全になくすことも難しい。
- 睡眠が邪魔されていたり、仕事に大きな支障があるようなら病院受診を検討。また期間が1か月近く続くようなら受診を推奨。
- 人にうつる咳は、おおよそ発症から10日前後まで。1か月以上続いてなお人にうつすものは稀。
- 咳の発症からの期間で、急性・遷延性・慢性に分けられる。原因がそれぞれ異なってくる。
- 急性期の咳は、1か月めどで自然消失する。
- はじめは風邪症状と思っても、1か月続くようなら違う病気も考える。ただし「1か月続く」なので、思ったよりも長く続く場合ととらえる。
今回は咳についてまとめてみました。
今後咳が出たときには、どのくらい症状が日常生活を邪魔しているのか、症状がどのくらい続いているのか、を踏まえて 病院に行くのか、市販薬で様子を見てみるかの判断材料にしてみてはいかがでしょうか。
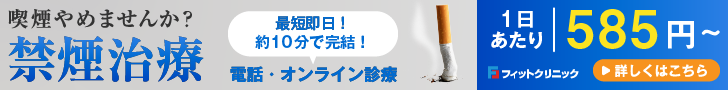


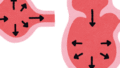
コメント