口から食事が摂れなくなったとき、栄養をどのように補給するか(人工栄養)の選択は、ご本人にとってもご家族にとっても非常に大きな決断です。
人間の生命活動の1つであり、尊厳でもある食事。
口から食べるということは、基本的なことですが、実は複雑に連続した行為を無意識にやっています。
そのため、脳の病気や認知症などで、機能低下するとうまく飲み込めず「誤嚥」が発生します。
病気が改善したり、リハビリで機能が回復していけば、また口から食べることができるようになりますが、
高齢などの理由で回復できない機能低下まで落ちてしまうこともあります。
「口から食べられなくなった時に、どんな方法があるの?」
「難しい方法なの?負担はかかるの?」
「どんな生活になってしまうの?どのくらい生きてられるの?」など様々な疑問が出てきます。
このページを含め、これから数回に分けて解説し、全ての疑問が解消します。
口からの食事の代わりをするために、大きく手段が2種類あります。
口の代わりに別の方法で、消化管に栄養剤を送る(胃ろう、経鼻胃管)方法、
消化管すら使わず、血管の中に直接栄養成分を入れる中心静脈栄養(ここも2つに分かれ、CVポート造設と造設せず中心静脈カテーテルを入れる方法)をする方法です。
第1回目は、それぞれの概略をご紹介します。具体的なランキングは次回以降に発表します。

胃ろう 一番有名な方法
胃ろうは、おなかの外から直接胃にチューブ(管)を通して栄養を入れる方法のことで、
胃とお腹の皮膚の間に作られる小さな穴を「ろう(瘻)」と呼びます。
造設するには、お腹の表面から内視鏡の画面を確認しながら胃の中と皮膚をつなげて、その後チューブを留置します。
内視鏡(胃カメラ)と場合によりレントゲンを併用しながら、なるべく安全に作成されています。
おおよその時間は、直前の準備などを含めても1時間以内で終了します。
造設時の負担は、表面からの穿刺・切開、チューブを通すときなどの疼痛とその時に使う局所麻酔や点滴麻酔の影響、内視鏡を行う影響です。
造設時の合併症は、切開などでの出血、誤穿刺(腸管、血管、肝臓など)、麻酔アレルギーなどです。
造設後1週間程度経過した後に、胃ろうの瘻孔周囲が感染したり、栄養剤が漏れてくることなどです。
胃ろうの交換は、使うものにもよりますが、おおよそ6か月前後で交換することが多いです。
この時は、レントゲン併用か内視鏡を併用するかは、行う病院により異なりますが、基本的には外来処置で終わります。

経鼻胃管:鼻からチューブを入れる
経鼻胃管とは、鼻からチューブを喉に入れ、さらに食道・胃まで先端を進め、留置する事です。
鼻から出ているチューブから栄養剤を入れると、胃の中に栄養剤が届きます。
鼻からチューブを入れるだけなので、特に体を傷つける必要はありません。
また内視鏡なども使用せず、ベッドサイドで入れることができます。
入ったかの確認でレントゲンを1枚撮影して終わることが多いです。
負担は、入れるときの疼痛・違和感、留置した後の異物感があります。
また留置しているチューブの周りに唾液がくっつき、唾液による誤嚥が増える可能性があります。
交換は2週間~1か月に1回することが多いです。交換自体も留置するときと手技は同様です。

CVポート:中心静脈をするときに、針を刺す基地をつくる
CVポートとは、中心静脈カテーテルの端にポートと呼ばれる針を刺す場所がくっついています。
ここに針を刺せば、カテーテルにつながっており、血管内に栄養成分が点滴できるというものです。
中心静脈栄養の合併症の1つに、感染症があります。
体表面から細菌が入ることが大半で、なるべく外部のものとカテーテルを触れさせたくないのです。
そのため、ポートを皮下組織に埋め込む手術をして、直接外部と触れさせないようにします。
ポート部に触れるのは針先だけで、しかも1日1回交換していれば衛生的に使用できます。
ポートを埋め込むため、胸部の肩付近や首元の皮下組織を広げる必要があり、局所麻酔をして切開を加えていきます。
処置時間は1時間程度ではないかと思います。
処置の合併症は、出血が一番多く、他に感染や皮膚縫合不全があります。
長く中心静脈栄養が必要な場合は、留置していると感染率が徐々に増えていくため、ポート留置の方が、処置後の感染率が低くできます。
交換も感染がなく、カテーテル閉塞しなければ不要です。
中心静脈カテーテル留置:直接皮膚にカテーテルをつなげる
中心静脈カテーテル本体を直接皮膚から血管に通して留置するものです。
点滴の大きなバージョンのように思ってください。
留置する場所は首、鎖骨下、大腿部(鼠径部)から選ばれることが大半です。
処置自体は局所麻酔のみで、点滴と同じような手技を少し工夫しながら留置していきます。
早ければ15分前後で終わると思います。穿刺部によって合併症が異なりますが、首・鎖骨下で行う場合、肺が近くにあるので、気胸を起こす場合があります。
留置後の合併症で一番多いのは感染です。
カテーテル留置後、どんなに気を付けても感染リスクは日がたつごとに上昇してしまいます。
感染時は交換などで対応しますが、早ければ2週間前後でも感染していく場合もあります。
長期留置にはあまり向かない手段ではあります。
まとめ
口から食事がとれなくなった時の代わりの方法として、胃ろう・経鼻胃管・CVポート・中心静脈カテーテル留置について概説しました。
メリット・デメリット比較表
それぞれの違いを一目で比較できるようまとめました。
| 項目 | 経鼻胃管(鼻チューブ) | 胃ろう | 中心静脈栄養(CV/TPN) |
| 侵襲(体の負担) | 小(手術なし) | 中(内視鏡手術あり) | 中(カテーテル留置処置あり) |
| 期間の目安 | 短期(〜4週間) | 長期 | 長期も可 |
| 本人への苦痛 | あり(喉の違和感、見た目) | 少ない(服の下に隠れる) | 少ない(点滴のみ) |
| 管理のしやすさ | 難しい(抜けやすい) | 容易 | 難しい(感染管理が必要) |
| 感染リスク | 誤嚥性肺炎のリスク(大) | 瘻孔(穴)の皮膚トラブル 誤嚥性肺炎リスク(小) | カテーテル感染(敗血症など) |
| 入浴 | そのまま可 | そのまま可 | 注意が必要(濡らせない等) |
| 腸の機能 | 維持できる | 維持できる | 低下する(腸を使わないため) |
次回以降で、どの方法が一番良さそうなのかランキング形式で発表します。
第2回:口から食べられなくなった。代わりの方法ランキング 「栄養」編
第3回:口から食べられなくなった。代わりの方法ランキング 「本人の負担」編
第4回:口から食べられなくなった。代わりの方法ランキング 「自宅で長くいたい」編
番外編:口から食べられなくなった。代わりの方法は?終末期に選択する方法
それぞれ長所、短所がありますので、皆様も整理してみてくださいね。

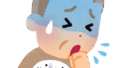
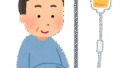
コメント