第1回目では口から取れなくなった時に、代わりにする方法をご紹介しました(別記事:第1回:口から食べられなくなった。ご紹介編)。
今回は栄養が一番有効に取れるのはどれかをランキング形式で並べてみます。
並べるのは胃瘻、経鼻胃管、CVポートと中心静脈栄養の3つです。
前回はCVポートと中心静脈栄養を分けて説明しましたが、血管に直接栄養成分を入れるという点では同じなので、今回はひとくくりにしています。
また栄養を吸収するには、胃瘻と経鼻胃管は腸管の機能が働かないとダメですが、今回は使用できるものとと仮定しています
栄養療法の「鉄則」:「腸が動いているなら、腸を使う」
まず、栄養療法には**「鉄則」があります。それは「腸が動いているなら、腸を使う」**ということです。
- 経腸栄養(胃ろう・経鼻): 腸を使って消化吸収させる。免疫機能が維持されやすく、体に自然。
- 静脈栄養(中心静脈): 腸が使えない場合の手段。血管から直接栄養を入れる。
第1位:胃瘻 腸管が使えるなら、ゼリー形態でも入れることができる
腸管からの栄養剤投与と血管に直接栄養剤を投与する方法で、
どちらが栄養として使われるかとなると、腸管からの栄養>血管からの栄養となります。
- 生理的である:体の自然な栄養経路
- 栄養剤として十分な種類がある:点滴ではまだ投与できない成分も吸収できます
- 免疫維持に役立つ:腸管自体が、体の免疫機能と深くかかわっており、腸を使うことで免疫機能が刺激され、全身の免疫の活性化にもつながります。
- 腸の機能を保つ:腸粘膜を刺激することで、腸の萎縮を防ぎ、バリア機能を保ちます。
- 感染リスク:点滴と比べて、腸管から感染することは少なめ
このため、腸が使えるなら胃瘻・経鼻胃管が中心静脈栄養よりも優先となります。
胃瘻と経鼻胃管の差は、栄養の吸収においては同じことであり、特に差がありませんが、
この二つで優劣をつけるなら、消化管に到達するまでの長さが一つ要因として挙げられます。
胃瘻は体内にあるチューブの長さは長くても4㎝前後ですが、経鼻胃管は鼻から少なくとも50㎝程体内にチューブを入れて、胃の中に到達します。
チューブ自体は細いので、栄養剤が液体ならそこまで差がなく投与可能ですが、ゼリー状であったりすると短いほうが入れやすくなります。
また経鼻胃管では、チューブが少しずれてせき込み、その後嘔吐するなど、何かと投与が不安定になることもあります。
投与時の安定性と栄養形態の種類がより多く選択できるという点で、
胃瘻>経鼻胃管と判断しました。

第2位:経鼻胃管 手軽ではあるけれど、交換・煩わしさはある
栄養という点では、煩わしさなどはありますが、それでも中心静脈栄養と比べると、腸管栄養が勝るため、第2位になります。
胃瘻よりは、長期的に不利であることもあり、基本的には短期間の使用にとどめるべきものではないかと思います。
ただ、胃瘻ができない人で腸管栄養をする場合はこちらを選択することになります。

第3位:中心静脈栄養 血管に栄養成分を入れても、すべてを利用できない
中心静脈栄養は理論上なら投与したすべてを利用できるはずですが、実際は60-70%程度しか利用できていない印象です。
栄養成分を代謝するところは主に肝臓ですが、中心静脈栄養を行うと、1-2週間後から徐々に肝機能障害が出てきます。
理論上血管内に必要な量を投与しても、体が受け止めきれず、うまく代謝・吸収されないという状況になっています。
それでも、何も栄養を取らないよりははるかによく、短期であれば特に問題なく使用できます。
中心静脈栄養の利点は、
- 吸収が不要:腸管機能がなくても大丈夫
- 投与量として、理論上の計算がしやすい:確実に血管内には届けられる
欠点は、
- 腸管を使わず1週間後程度から、腸管粘膜萎縮が始まり、免疫力の低下などが起きる。
- エネルギーの主はブドウ糖であり、血糖値が急上昇する場合がある。
- アミノ酸や脂肪成分を、必要量入れるのに、全体の水分量なども見ながら考える必要がある。
- 感染症になるリスクが常にある(血管内と外界が常につながっている状態)
腸管吸収の場合は、ある程度であれば自動で腸管が選別し、必要な分を調整してくれますが、
点滴の場合はその調整がないため、細やかにメニューを決めていくことになります。
まとめ:栄養投与においてのランキング
1位:胃瘻
2位:経鼻胃管
3位:中心静脈栄養(CVポートも含む)
栄養投与を第一に考えるとこのようになります。
ただ、発熱などで普段より水分量を追加したい場合、点滴なら容易に増やすことはしやすいですが、
胃瘻・経鼻胃管では水分を多くする→腸管により負担をかけるということになるので、
嘔吐したりうまく使えないこともあります。
病気の時に食欲がなかったり、無理して食べたら吐いたことも経験しやすいですよね。
第3回目は「本人負担が一番少ないのはどれか」について言及します。
以下はこのシリーズの別記事です。良ければご覧ください。
第3回:口から食べられなくなった。代わりの方法ランキング 「本人の負担」編

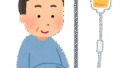
コメント